敬老の日に送る実用的なプレゼントの選び方や、敬老の日は何歳から祝うのか、手作りメッセージカードの簡単な作り方まで!短くサクッとご紹介します。
今のうちにチェック!口コミで大人気の桐箱ギフト、贈り物選びで迷わなくてすみますよ♪
↓ ↓ ↓
この記事のポイント
・実用的ギフトの選び方(用途・予算)
・祝う年齢の目安と家族での決め方
・短時間で作れる手作りメッセージカード例
・贈る前の確認リスト(アレルギー・好み)
それでは早速見ていきましょう(^^)/
敬老の日のプレゼント!喜ばれる定番10選と選び方のコツ

「プレゼントを贈りたいけど、何を選んだら実用的なのか迷っちゃいます…。」

「そうですよね。毎日使ってもらえるものを考えると、選びやすくなりますよ。一緒に定番の例を見ていきましょう。」
敬老の日に贈るプレゼントは、おじいちゃんやおばあちゃんが日常生活で役立つものを選ぶと特に喜ばれます。実用的で使いやすい贈り物は、受け取った後に長く活用してもらえるので安心です。ここでは人気が高い定番アイテムと、失敗しにくい選び方の工夫について紹介します。
実用的プレゼントの「使いやすさ」と「長く使える」を見るポイント
贈り物を考えるときに大切なのは、毎日使えるかどうかです。例えば食器やタオルは生活の中で必ず出番があり、どの年代の方にも喜ばれる傾向があります。
また重さや扱いやすさも重要です。軽くて持ちやすい物や、お手入れが簡単な品は長く使ってもらえます。さらに、シンプルなデザインや落ち着いた色を選ぶことで、好みに左右されにくく安心です。
贈り主の気持ちを伝えながらも、相手が生活に取り入れやすいかを考えるとよいでしょう。
食品・日用品・健康グッズ…ジャンル別で選ぶおすすめ例
食品は消耗品なので物が増えず、もらう側にとっても気軽に受け取れる点が強みです。例えば高級なお茶や和菓子は定番で人気があります。
日用品では上質なタオルやおしゃれな食器が役立ちますし、実際に使うことで贈り物を思い出してもらえます。健康グッズでは体に負担をかけないクッションやリラックスできる枕などが選ばれています。
どのジャンルも「普段の暮らしを少し快適にするもの」を意識すると、自然と喜ばれるアイテムに近づけます。
贈る前に確認すること(アレルギー・好み・取り扱いの注意)
せっかくの贈り物も、相手の体質や生活習慣に合わなければ負担になってしまいます。食品を贈る場合はアレルギーや持病に影響がないかを確かめておくと安心です。
日用品であれば、色や素材の好みを事前にリサーチしておくと失敗を避けられます。健康グッズなど機械を使うものは操作が難しくないかも確認が必要です。
贈る相手の立場に立ち、普段の生活に自然となじむかを考えて選ぶことが大切です。気遣いが伝われば、それだけで気持ちのこもった贈り物になります。
予算別に選びやすい実用的ギフト例
| 予算帯 | プレゼント例 | 特徴 |
|---|---|---|
| ~3,000円 | お茶・和菓子セット、靴下、タオル | 気軽に贈れる、日常的に使える |
| 3,000〜5,000円 | 名入れマグカップ、健康茶、軽量食器 | 実用性と特別感を両立 |
| 5,000円〜 | 血圧計、上質な寝具、食品ギフト詰め合わせ | 長く使えるものや健康を意識した品 |
バームクーヘンやマグカップも選べるから、贈る相手に合わせてピッタリのセットが見つかりますよ。
↓ ↓ ↓
敬老の日、何歳から祝う?公的な目安と家族で決める賢い判断

「敬老の日って、何歳からお祝いすればいいのかちょっと分からなくて…。」

「たしかに年齢の基準は人によって違いますよね。実際によくあるタイミングを見てみると、イメージしやすくなりますよ。」
敬老の日は感謝の気持ちを伝える日ですが、「何歳から祝うのか」は家庭によって異なります。法律や国の制度に明確な決まりはなく、公的には65歳以上を高齢者とする基準が一般的です。
実際には孫が生まれたときや、還暦など節目の年齢をきっかけに始める家庭もあります。大切なのは形式よりも気持ちであり、相手が喜んで受け取れるタイミングを見極めることです。
公的な目安と慣習の違い(年齢で区切らない実務的な見方)
敬老の日を祝う年齢に法律上の決まりは存在しません。老人福祉法では65歳以上を高齢者としていますが、これはあくまで行政上の目安です。
一方で、日本では還暦や古希といった長寿祝いをきっかけに敬老の日を意識する人も多くいます。つまり「65歳になったら必ず祝う」といった厳しい線引きは不要で、あくまで家族や本人の気持ちが優先されるのです。形式にとらわれすぎず、自然に感謝を表す機会と考えると良いでしょう。
地域差・世代差に配慮するポイントとトラブル回避法
年齢の受け止め方には世代や地域による違いもあります。都市部では「まだ若いから」として早い段階で祝われることを好まない人もいますし、地方では60歳を過ぎたら自然に敬老の日を祝う習慣が残っていることもあります。
こうした違いを無視すると、相手を驚かせたり気分を損ねたりする恐れがあります。お祝いを考える際は、直接聞いたり家族間で相談したりして、相手の気持ちを尊重することが大切です。配慮を欠かさなければ、無理のない自然なお祝いになります。
「祝う・祝わない」を決めるときの具体的な判断基準
いつから敬老の日を意識するかを決めるときは、相手がどう受け止めるかを軸にすると迷いにくくなります。例えば孫から贈り物をしたい気持ちが強ければ、本人がまだ若いと感じていても「ありがとう」の気持ちを添えて渡せば受け入れやすくなります。また、還暦や古希といった節目の年齢をひとつの目安にするのも方法です。
最も大切なのは「無理に祝うのではなく、自然に感謝を伝える機会」と考えること。柔軟に判断する姿勢が、良い関係につながります。
写真を送ったあともイメージ図を見せてもらえるから、仕上がりまで安心して任せられます。
↓ ↓ ↓
手作りメッセージカード!簡単:短時間で感動させる作り方3ステップ
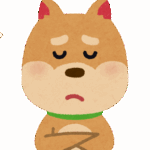
「手作りのカードって喜ばれそうだけど、不器用だから上手にできるか不安です…。」

「大丈夫ですよ。手の込んだ作品じゃなくても、気持ちを込めるだけで十分なんです。簡単な流れをチェックしてみましょう。」
手作りのメッセージカードは、材料が少なくても気持ちをしっかり伝えられるのが魅力です。特別な道具がなくても、紙や写真、折り紙など身近なものを使えば温かみのあるカードを作れます。ここでは時間がなくても作れる簡単なアイデアと、相手の心に残る工夫を紹介します。
材料3つでできる!孫の写真や手形を使った簡単カード例
カード作りで一番喜ばれるのは、子どもや孫の成長が感じられるデザインです。画用紙、のり、はさみの3つだけでも十分に仕上げられます。
例えば手形をカラフルにスタンプして花の形にしたり、孫の写真を切って台紙に貼るだけでも立派なカードになります。文章を添えなくても「大好き」「ありがとう」など一言を書き添えるだけで気持ちは伝わります。難しい工作が苦手な人でも取り組みやすく、手作りならではの温もりを感じてもらえる方法です。
短くても心に響く文例集(親しさ別・シーン別)
長文を書く必要はありません。むしろ短くても気持ちがこもっていれば十分伝わります。
親しい祖父母には「いつもありがとう、また一緒に遊ぼうね」といった温かい言葉が効果的です。少し距離のある関係なら「体に気をつけて、いつまでも元気でいてください」といった丁寧な表現が安心感を与えます。特別なイベントが近い場合は「今度の集まりで会えるのを楽しみにしています」と加えると先の楽しみも共有できます。
シーンや距離感に合わせて工夫することが大切です。
| 関係性 | 文例 | ポイント |
|---|---|---|
| 親しい祖父母 | 「いつもありがとう、また遊ぼうね」 | 温かくフレンドリーな表現 |
| 少し距離がある | 「体に気をつけて、元気にお過ごしください」 | 丁寧で安心感を与える |
| 特別なイベント前 | 「今度の集まりで会えるのを楽しみにしています」 | 未来への期待を共有 |
苦手な人向け:テンプレート&印刷サービスで手早く仕上げる方法
手作りに自信がない人は、デザインテンプレートを活用すると安心です。インターネット上には無料で使える素材が多く、写真やメッセージを入力するだけで本格的なカードが完成します。自宅のプリンターで印刷してもよいですし、オンライン印刷サービスを使えば高品質な仕上がりになります。
既成のデザインを利用しても、手書きで一言添えると特別感が生まれます。無理をせず、手軽に気持ちを伝える方法を選ぶことで、相手に喜ばれるカードに仕上げられます。
世界にひとつのギフトだから、実際に選んだママさんたちからも喜びの声がいっぱい♪
↓ ↓ ↓
毎日役立つ贈り物で喜ばれる秘訣
敬老の日の贈り物は「実際に使えるもの」が一番喜ばれます。特別な記念品よりも、毎日の生活で役立つアイテムを選ぶと自然に感謝の気持ちが伝わります。ここでは暮らしを少し快適にしてくれる実用的なプレゼントを紹介します。
健康をサポートする日用品(血圧計・歩数計・温熱グッズなど)
高齢の方が日常的に健康を意識できるグッズは、安心を届けられる贈り物です。血圧計や歩数計は体調管理に役立ちますし、温熱グッズやひざ掛けは冷えを防いで快適に過ごせます。使い方が簡単でシンプルなものを選ぶのがポイントです。
毎日無理なく使えるので、贈る側も「役立っている」と実感でき、相手にとっても生活の支えになります。
食事がもっと楽しくなる!食品系のプレゼント
食べ物の贈り物は実用性が高く、誰にでも喜ばれる定番です。高齢の方には柔らかくて食べやすい和菓子や、健康を意識したお茶やスープなどがおすすめです。普段は買わない少し特別な味を選ぶと、贈られた側の気分も華やぎます。
食べ物は消え物なので気を遣わせず、冷蔵や常温保存ができるタイプを選べば安心です。楽しい食事の時間を演出できる点が魅力です。
生活を快適にするファッション小物やインテリア雑貨
毎日使うタオルや靴下などのファッション小物も、実用的で人気があります。上質な素材のタオルは肌触りがよく、日常に小さな贅沢を添えてくれます。
インテリア雑貨では、使いやすいマグカップや軽い食器などもおすすめです。相手の好みに合わせやすく、無理なく取り入れられるのが強みです。実用性に加えて見た目も楽しめるものを選ぶと、生活に彩りが生まれます。
実際に買った人のレビュー評価がすごく高くて、「宝物になった」って声もたくさんありました。(^^)
↓ ↓ ↓
贈り物やメッセージを贈るタイミングとは
敬老の日は「何歳から祝うのか」がはっきり決まっているわけではありません。年齢で線を引くのではなく、祖父母になったタイミングや、家族で「ありがとう」と伝えたいと思った時が始めどきです。ここでは実際に祝う目安や考え方を紹介します。
一般的に多いのは60歳前後からのお祝い
| 年齢の目安 | お祝いのきっかけ | よくあるケース |
|---|---|---|
| 60歳前後 | 定年退職 | 還暦祝いとあわせて敬老の日を始める |
| 孫が誕生した時 | 家族構成の変化 | 初孫からカードやプレゼントを贈る |
| 65歳以上 | 高齢者の一般的な区切り | 公的な統計や制度上の目安として多い |
多くの家庭では60歳前後を一つの目安にしています。ちょうど定年退職の時期と重なるため、「第二の人生のスタート」として感謝の気持ちを伝える人が多いです。
ただし、年齢にこだわらずに「孫が生まれたからおじいちゃんおばあちゃんになった記念」として祝うケースもよくあります。形式ばらず、家族で話し合って決めるのが自然です。
年齢よりも「孫ができた」ことが祝うきっかけになる
実際には年齢に関係なく、初めて孫ができた時からお祝いを始める家庭も少なくありません。孫からの「ありがとう」は何よりも特別で、どんな高価な贈り物より心に残ります。初めて「おじいちゃん」「おばあちゃん」と呼ばれたタイミングで手作りカードや簡単なプレゼントを贈ると、忘れられない思い出になります。
無理に年齢で区切らず家族で自然に始めるのが一番
「まだ若いのに敬老の日と言われるのは抵抗がある」という人もいます。そのため、無理に年齢で区切るよりも「気持ちを伝えたいと思った時に祝う」方が自然です。
大切なのは年齢ではなく、家族の絆を深めるきっかけになること。形式よりも気持ちを重視して、相手が喜ぶ方法でお祝いするのがおすすめです。
まとめ
この記事を読めば、実用的で失敗しにくい敬老の日ギフト選びの要点と、何歳から祝うかの判断、さらに簡単に作れる手作りメッセージカードのコツが手早く分かります。以下のポイントを押さえれば当日の準備がスムーズになります。
・実用的ギフトは消耗品や日常品が喜ばれる
・食品は物が増えず気軽にもらえるメリットあり
・健康系は簡単操作と安全性を最優先に選ぶ
・名入れやパーソナライズで思い出に残るギフトにする
・予算目安は段階分けで選びやすくなる(〜3,000/3,000〜5,000/5,000〜)
・何歳から祝うかは法的決まりがないため家庭で柔軟に判断する
・公的目安としては65歳が広く用いられるが家族の意向を尊重する
・手作りカードは材料を絞り孫の写真や手形を活用すると感動度アップ
・テンプレや印刷サービスを使えば短時間で仕上がる
・贈る前にアレルギー・好み・使い方の確認を行う
相手の日常を想像して選べば、それだけで心に残る贈り物になります(^v^)
数量限定の“写真入り宝箱ギフト”、贈り物に迷っているなら早めにチェックがおすすめです♪
↓ ↓ ↓
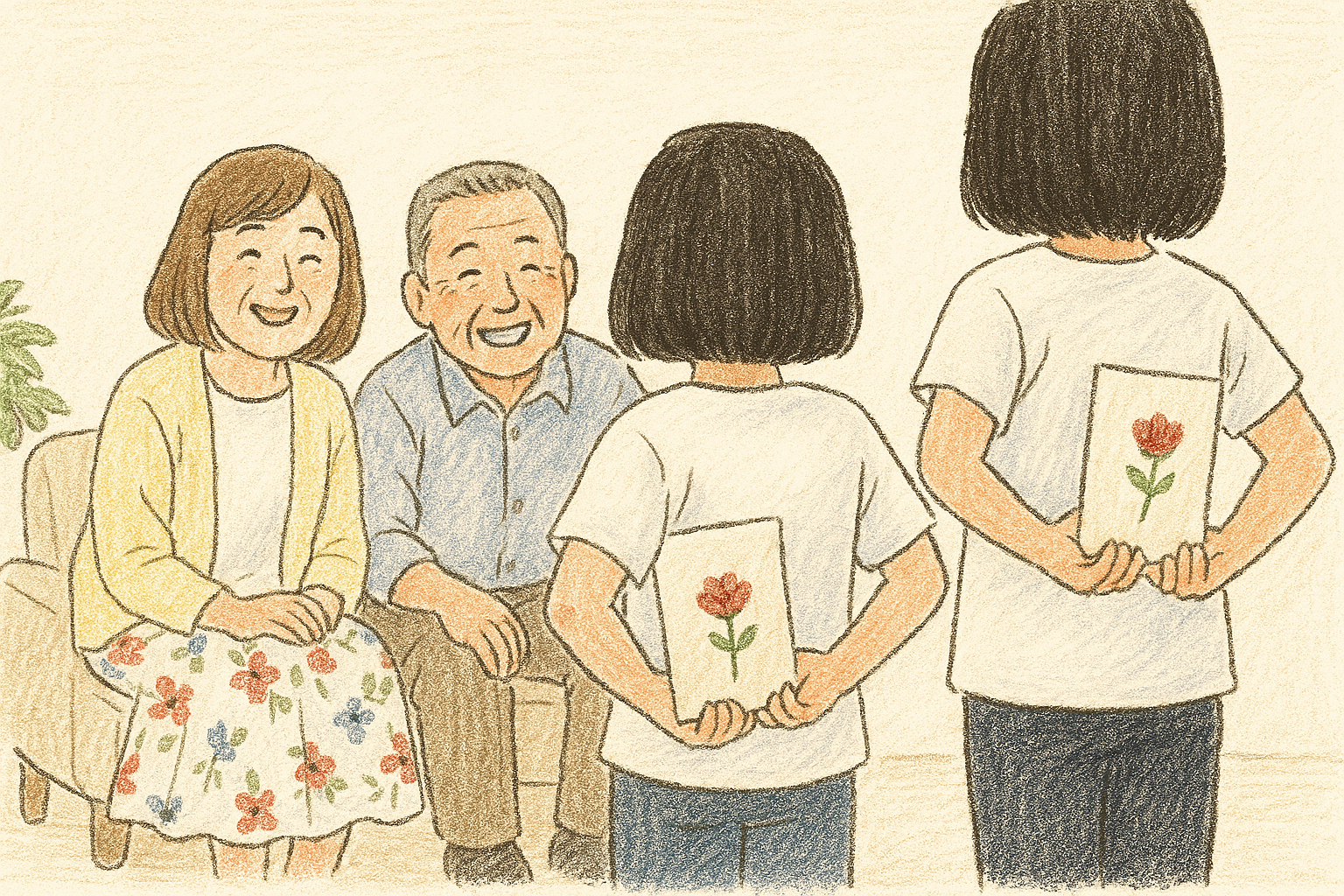
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bf801d2.fb5327d6.4bf801d3.b58d2f0c/?me_id=1331766&item_id=10001016&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Firohaya-namepoem%2Fdetail%2F25takarabaco-f.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bf801d2.fb5327d6.4bf801d3.b58d2f0c/?me_id=1331766&item_id=10001016&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Firohaya-namepoem%2Fdetail%2F25takarabaco-f_3.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bf801d2.fb5327d6.4bf801d3.b58d2f0c/?me_id=1331766&item_id=10001016&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Firohaya-namepoem%2Fdetail%2F25takarabaco-f_2.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bf801d2.fb5327d6.4bf801d3.b58d2f0c/?me_id=1331766&item_id=10001016&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Firohaya-namepoem%2Frankstamp%2Fsp%2Ftakarabaco-f.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bf801d2.fb5327d6.4bf801d3.b58d2f0c/?me_id=1331766&item_id=10001016&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Firohaya-namepoem%2Fdetail%2F24takarabaco-f_i2.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bf801d2.fb5327d6.4bf801d3.b58d2f0c/?me_id=1331766&item_id=10001016&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Firohaya-namepoem%2Fdetail%2F25takarabaco-f_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

コメント